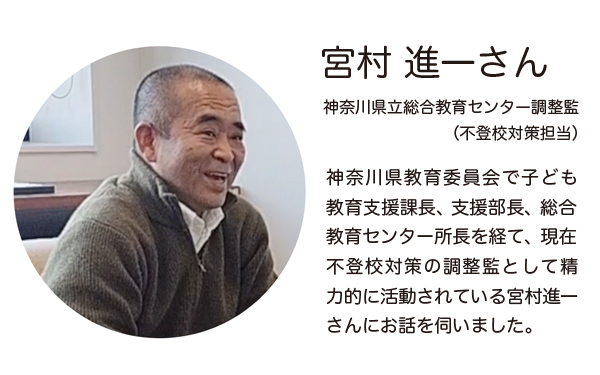
「もっと先生方と対話をしていきたい」
現在の仕事は、一言で言うと「神奈川県における不登校対策の取り組みに係る調整役」。
県の教育委員会は規模が大きく部署がいくつも分かれているので、どうしても情報共有や意見交換が難しい。そこを埋めていくのが私の役割。また、県教委の基本的な考え方が先生方に浸透していくように伝えていくことも役割の一つ。
例えば、県立総合教育センターの事業として「カリキュラム・コンサルタント」というものがあり、今年度は学校や市町村教委、教育事務所等からの要望を受けて 30か所ほどで話をしています。
不登校だけでなくいろいろなテーマで話しますが、必ず児童生徒指導や支援教育の話をします。もっと先生方と深く対話をもちたいが、時間が足りない。かわりにアンケートを必ず書いてもらい、先生方の声を次に活かすようにしています。
「支援教育は子どもたちを『ちやほや』『ヨイショ』すること?!」
30代の先生との対話。「県の『支援教育』とは?」の問いへの返答がこの言葉。ショックでしたが、これもまた現実なのかもしれないと。
例えば生徒指導の世界でよく使われる「服装の乱れは心の乱れ」という言葉も然り。元来の「服装の乱れからその生徒の心の乱れを見立て、心を整えるために必要な支援を行っていく」という意味が、いつしか、「服装の乱れは心の乱れに繋がるので、とにかく服装を正していく」と曲解されてきた、というように、目的と手段が本末転倒とならぬよう、絶えず「あたりまえ」を疑い、見直し、共有していくことが重要。
また、「授業規律」という名のもとに、学校が「同調圧力」「正解主義」に陥っていないでしょうか。先生方が、従来の「あたりまえ」を議論したり共有したりしないまま日々が過ぎていくことに危機感を感じます。大人目線の既存の物差しに、先生方がとらわれてしまっている。
今こそ大切にしたいのは、子ども目線での「真面目な雑談」。
お互いの多彩な考えを交わしていくことで学校はよりよく変わっていくと思います。
子どもと直接関われた若い時は、失敗もたくさんありましたが、保護者の方や先輩、管理職の先生方に恵まれたおかげで、いろいろと挑戦できました。
平成14年に特別支援の研修で知った「『困った子』は『困っている子』」の理念。当時、「目から鱗」でした。その言葉を心の底に置いただけで、特に何をしたわけでもないのに、翌日から子どもたちの様子がガラッと変わった。伝わるんですよね。
「学校風土」は、校長によるところが大きいですが、教職員一人ひとりのパーソナリティ、関係性によるところも大きいですし、地域との関係性によるところもあるでしょう。
また、「子どもの人権」について、知識としてあったとしても、日々の現場で起こる様々な場面に当てはめ、ふりかえって考えることはあるでしょうか?
子どもは大人を本当によく見ています。

「神奈川県学校・フリースクール等連携協議会」
神奈川県の不登校支援の特色として、来年度20周年となる神奈川県学校・フリースクール等連携協議会があげられます。
連携協議会発足前の平成14年、あるフォーラムで当時の県教委の部長が「学校がつらかったら行かなくてもいい」と話したのは、衝撃的な出来事でした。その後、連携協議会が始まってからも、当初はフリースクール等と教育委員会はお互い疑心暗鬼だったし、かなり意見を戦わせてきました。しかし、その後も対等な関係で真剣な議論を重ね、ともに
相談会を運営するなど交流を継続してきたからこそ、今の「顔が見える関係」があり、神奈川県独自の不登校支援があります。
フリースクール等は「子どもを待つ」ということや雰囲気が学校と全く違う。そして人権意識が違う。子どもたちとのこうした関わり方から学ぶことが大いにあります。ぜひ、各
学校は地域のフリースクール等との連携をすすめていってほしいです。
「キミイロ」
「キミイロ」は、神奈川県教育委員会だけでなく、連携協議会とも協働で事業をすすめてきました。
これまでの教育委員会とフリースクール等との関係性があってもなお、企画提案から約一年、慎重な協議期間を経て、県教育委員会と認定NPO法人鎌倉あそび基地フリースクー
ルLargoの協働による「キミイロ」の制作がはじまりました。
コロナで県の不登校相談会が開催できない時期はオンライン不登校相談会を開催、「キミイロ」上で予約できるようにして実施しました。
また昨年度は、連携協議会企画委員会のメンバーと教育委員会支援部長による座談会を収録し、3回シリーズで「キミイロ」上にアップしました。フリースクール等と教育委員会
の部長が不登校について対等に語っているあの動画を、「キミイロ」から発信できた意義は大きく、内容を重く受け止めています。県のHPでは実現できないことだったかもしれ
ません。この「キミイロ」は、不登校の子どもたちやその保護者の方など「当事者の目線に徹底的に寄り添った発信源」であるという点に、大きな価値があると考えています。
「不登校対策は元気な学校づくり」
近年、高等学校の不登校も課題となっています。「高校は義務教育でないから」という認識を変えていく必要があると考えています。
「日々の授業、活動の一つひとつを、いかに子ども目線で実施できるか。」「『この子』が学校に行ける学校づくりは、どうしていけばいいのか?そのためには?」
学校は、従来の「あたりまえ」を省みて、子どもたちと共に考え議論し実行していく中で、新たな不登校を生まない「元気な学校」へと成長していくのではないでしょうか。
子どもたちと分かち合う喜び、卒業式で子どもの成長した顔を見られる、あの瞬間。
教師という仕事は、春夏秋冬を感じられる仕事、喜怒哀楽を感じ表現できる仕事。
「こんなに自分の生の感情が湧き上がってくる素敵な仕事は他にない。」
そう思っています。
不登校支援が不要となる日が一日も早く来ることを願っています。
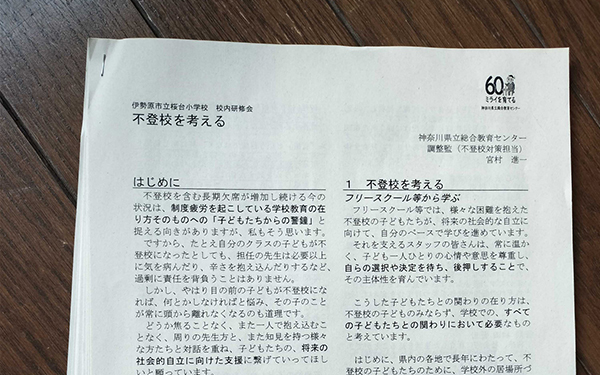
※「いつも時間切れで伝えきれないから・・」と各地でお話しする際に配布するという、思いの詰まった研修資料。
宮村さんの子どもたちへの思い、先生方への期待が込められています。
